走力を科学する、最強のトレーニング理論
マラソンを走るすべてのランナーにとって、トレーニング方法は永遠のテーマ。その中でも「最も科学的」と名高いのが、ジャック・ダニエルズ博士による『ダニエルズのランニング・フォーミュラ』です。
この理論、単なる練習メニュー本ではありません。ランナーの走力を数値化する「VDOT」を軸に、明確な目的をもった5種類のトレーニングペースを使い分けることで、効率的に力を伸ばしていく超実践的な内容なんです。
この記事では、ダニエルズ理論の概要から、他の有名トレーニング理論との違い、そしてサブ3ランナーに向けた活用法まで、わかりやすく紹介していきます!
ダニエルズ理論の核「VDOT」とは?
まず押さえておきたいのが、**VDOT(ブイドット)**という概念。簡単に言うと、「走力の総合スコア」のようなもので、最近のレースタイムから算出されます。
例:10kmを45分で走った人は、VDOT 45くらいになります。
このVDOTを基準に、5種類のトレーニングペースが導き出されます。
5つのトレーニングペース
| ペース | 名称 | 目的 |
|---|---|---|
| Eペース | Easy(イージー) | 基礎持久力の向上・疲労回復 |
| Mペース | Marathon(マラソン) | レースペースへの慣れ |
| Tペース | Threshold(閾値) | 乳酸処理能力の向上(持久的スピード) |
| Iペース | Interval(インターバル) | 最大酸素摂取量(VO2max)の向上 |
| Rペース | Repetition(レペティション) | ランニングエコノミー・スピード強化 |
各ペースに役割があり、これらをバランスよく組み合わせることが最強の練習になるというのがダニエルズの教えです。
他理論とどう違う?マフェトン/リディアードとの比較
✅ 共通点
- 有酸素ベースを重視する(まずはしっかりジョグ)
- フォームや心拍ゾーンへの意識がある
❌ 違い
- マフェトン理論:低心拍ゾーンしか使わない。糖質制限と組み合わせる。
- リディアード理論:トレーニングを「期分け」していく(有酸素→坂道→スピード)
- ダニエルズ理論:VDOTを使って、練習ごとに明確な狙いを持たせる。すべてのペースをバランスよく取り入れる。
つまりダニエルズ理論は、理論のミックスと精密化によって進化したハイブリッドな存在とも言えます。
サブ3を目指すなら、こう使え!
サブ3(=フルマラソン2時間59分以内)を目指すなら、必要なVDOTはだいたい54~57。これを目標にトレーニングを組み立てていきましょう。
💡 週の練習例(週5走る場合)
- 月:Eペースジョグ(60分)
- 火:休養 or 軽いジョグ
- 水:Tペース走(20分間 or 3km×2)
- 木:Eペースジョグ(60分)
- 金:Iペースインターバル(1km×5)
- 土:休養
- 日:ロング走(E→Mペースビルドアップ)
最も大事なのは、「練習の目的をはっきりさせること」。
- 疲労回復?→Eペース
- レース後半の粘りを鍛えたい?→Tペース
- 心肺を鍛えたい?→Iペース
何のために走っているのかを理解している人ほど、サブ3達成に近づいていきます。
ダニエルズ理論を最大限活かすコツ
- 定期的にVDOTを見直そう(10km・ハーフのタイムでOK)
- 疲労が溜まってきたら迷わずEペースに切り替える
- ロング走はE〜Mペースで走るだけで充分強くなる
- すべてのペースに役割があることを理解する
まとめ:走力を”見える化”して、計画的に速くなる
ダニエルズ理論は、ただのトレーニング本ではなく、自分の走力を数値で理解し、それに合わせて練習の強度を調整するという、超論理的なツールです。
初心者にも、サブ3を目指すランナーにも、すべての人に使える。
「やみくもに走る」から卒業して、**“自分に合った速くなる方法”**で成長したいなら、この理論は間違いなく役立ちます!
✅ おすすめアクション
- 自分のVDOTを調べてみよう!
- 1週間の練習にT/I/Rペースを少しずつ取り入れてみよう
- 疲れたらEペースに戻ってOK。継続が最優先!
The Running Talkでは、今後もこうしたトレーニング理論や実体験に基づいたレビューをお届けしていきます!
感想や「この理論をどう実践してるか」など、コメントやSNSで教えてくださいね!
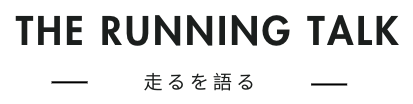


コメント